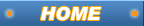 |
|
|
高橋会計事務所
|
 |
|
|
|
|
|
お問い合わせ
|
|
|
|
|
|
独立開業
|
|
|
|
|
|
千葉県の支援
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会社の種類 |
| 会社設立の費用 |
| 会社の決め事 |
| 法人成りのメリット |
| 法人成りの分岐点 |
|
|
|
給与計算
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税務調査の季節 |
税務調査が省略され
る場合 |
なぜ税務調査がある
か |
| 税務調査の種類 |
| 税務調査の対象期間 |
| 調査で何を調べる |
| 抜打ち調査について |
| 税務調査の当日 |
必要書類は事前に用
意 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資金繰り改善
|
|
|
税制改正
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
会社法 |
 |
|
|
|
会社法のあらまし
|
|
|
|
|
これにより今後の企業経営のあり方やビジネスのあり方が大きく変わる可能性があります。
この新会社法というは、旧会社法である商法(第2編「会社」)、商法特例法、有限会社法等の法律を改正して一本化したものです。
新会社法は「会社法制の現代化」ともいわれています。改正の中味には、形式面と実質面があります。
形式面で注目されるのは、法律の条文をこれまで「カタカナの文語体」であったものを「ひらがなの口語体」にしたことです。
これにより、これまで非常にわかりにくかった条文が読みやすくなりました。
商法は、その後に改正されているとはいっても、制定されたのは明治32年です。これを現代的な表現に書き換えたというわけです。
実質面でも、現代の社会経済情勢の変化に対応する抜本的な改正が行われました。
この中で、特に中小企業に大きな影響がある事項のうちの主なものは次の通りです。
|
|
|
|
イ. 有限会社制度の廃止
ロ. 最低資本金制度の撤廃
ハ. 合同会社制度の創設
二. 取締役や監査役などの「機関」の
置き方が柔軟化されたこと
ホ. 株式譲渡制限制度の改正
|
|
|
|
|
|
|
|
|
これらの改正の大きな流れにより、会社に対する規制が緩和され、経営の自由度が広がることになります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限会社制度が廃止となる
|
|
|
|
|
新会社法では有限会社制度がなくなるため、新たに有限会社は設立することができなくなります。
しかし、既存の有限会社がなくなるわけではなく、新会社法の「株式会社」(「特例有限会社」と定義されます)として存続することになります。
法律上は新会社法の「株式会社」として存続しますが、商号中には「有限会社」の文字を使用する必要があります。
特例有限会社は現行の有限会社に準じた措置がなされることになります。
株式会社への組織変更は、「有限会社」から「株式会社」への商号変更を行い、特例有限会社から新会社法に定める株式会社へ移行することにより行います。
手続としては、定款の商号を変更して、登記するだけです。
新会社法のもとでは、既存の有限会社は、有限会社としてそのまま存続するか、商号の変更により株式会社へ移行するかを選択することになります。
どちらを選択するかは自由ですし、いつまでに株式会社に変更しなければならないという規定もありません。
したがって、そのまま有限会社として存続する会社も少なくないものと予想されています。
また、一部には新会社法が施行される前に有限会社を設立しておこうという動きもあったようです。
というのは株式会社では最長年に1度は役員の登記をしなければなりませんが、有限会社では半永久的に役員の登記をする必要がないからです。
また、株式会社では決算広告が必要ですが、有限会社では必要がありません。株式会社に移行するためには、当然登記費用もかかります。
そのため株式会社という名称にこだわる必要がない場合には、有限会社として存続することを選択すべきものと思われます。
一方、対外的なイメージを重視する場合には株式会社へ変更すべきでしょう。株式会社のほうが当然イメージがよく、信用力があるように見えます。
また、有限会社では社債を発行することができませんが、株式会社なら発行可能です。
ところで、会社には法人税等がかかることになっていますが、その仕組はどんな会社であっても基本的に同じであり、
会社の種類によって法人税等に有利・不利はありません。
したがって、どの会社を選択するかは、誰が会社を運営するのかとか、使い勝手の良さなどを考慮して決定すべきことになります。
|
|
|
|
最低資本金制度が撤廃される
|
|
|
|
|
新会社法では最低資本金制度が撤廃されています。
これまで株式会社では資本金1000万円以上、有限会社では300万円以上が必要でしたが、この規制がなくなりました。
したがって、資本金1円の株式会社も設立可能となります。
これまでも経済産業省の新事業創出促進法で5年以内に資本金を増加させることを条件に資本金1円会社の設立が可能でしたが、
新会社法によりこれが無期限に続くことになります。
これにより、会社の設立が容易になるほか、有限会社から株式会社への移行もスムーズに行えるというわけです。
|
|
|
|
会社の機関設計が柔軟化される
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社を設立するときだけでなく、新株を発行するときの現物出資の要件も緩和されました。
例えば、社長個人が会社に対して貸付金がある場合、その貸付金をその額面金額以下で自由に現物出資できることになります。
これにより会社の負債を資本金に振り替えるデット・エクィティ・スワップ(DES)が簡単に行えるようになります。
これは会社再建策等の実務に大きな影響を与えるものと考えられます。
|
|
|
|
株式譲渡制限制度が改正される
|
|
|
|
|
株式譲渡制限とは、会社にとって好ましくない者が株主になることを防ぐために、
会社の承認がなければ自由に株式を譲渡することができないようにしたものです。
ほとんどの中小企業では、この株式譲渡制限制度を採っているものと思われますが、旧法では、相続があったような場合には、
譲渡の承認を受ける必要はなく、相続人に株式が移転してしまいました。
つまり、相続の場合には、株式の移転を阻止することができないため、会社にとって好ましくない相続人が株主になることもあり得たのです。
しかし、新会社法では、定款に「相続等による株式移転も会社の承認を必要とする」と定めておくことができます。
そうすれば、会社にとって好ましくない者が株主になることを阻止できるようになるわけです。
ただし、相続そのものは成立しますので、この場会には、会社がその株式(自己株式)を買い取ることになります。
これより会社を承継させたくないドラ息子の承継を阻止することができるようになります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市川市,我孫子市,船橋市,習志野市,千葉市,八千代市,佐倉市,四街道市,成田市,酒々井町,栄町,印旛村,本埜村,印西市,東金市,白井市,
鎌ヶ谷市,柏市,松戸市,浦安市 |
|
| Copyright (c) 2008 高橋会計事務所
All rights reserved.) |
|